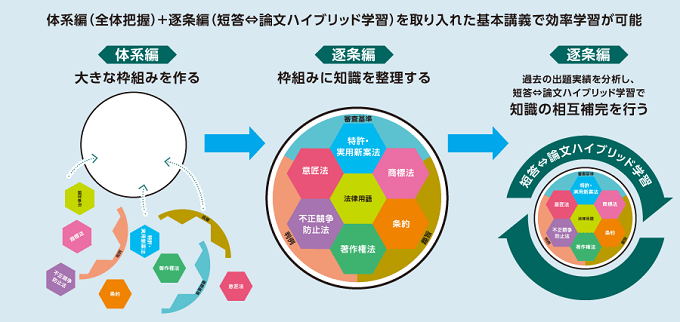弁理士試験は、一度の挑戦で合格するとは限りません。むしろ、何度も転び、失敗し、それでも立ち上がり続けた人こそが、最後に栄冠を手にする、そう語るのが、TAC弁理士講座の小松純先生です。
先生の座右の銘は「人生七転び八起き」。この言葉には、「人生とは敗者復活戦である」という強い信念が込められています。
挫折を経験した人ほど、次の一歩に意味がある。弁理士試験もまさにその連続であり、再び立ち上がる力こそが合格への原動力となります。
【動画】【TAC弁理士】令和8年度の弁理士試験に合格するために
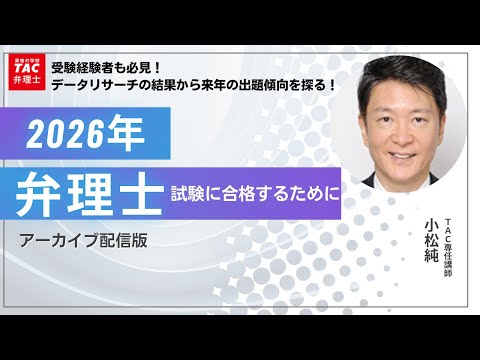
2025/06/25 #TAC弁理士 #弁理士勉強 #弁勉
TAC弁理士講座専任講師の小松純講師にお話しいただきました。お気軽にご視聴ください。
★当オンラインセミナーは2025年6月24日に実施されたものです★【TAC弁理士講座ホームページ】
https://www.tac-school.co.jp/kouza_be…
引用 YouTube
令和8年度試験を分析!今後の試験はこう変わる
短答試験は「39点の壁」を超える戦い
令和8年度の弁理士試験に挑むなら、まずは試験の全体像を理解することが欠かせません。
一次の短答試験はマークシート形式で、合格率は例年通り12.8%。注目すべきは「ボーダーラインが13年連続で39点」に設定されている点です。特許庁は毎年、およそ350人前後を論文試験へ進ませるため、この点数で線引きをしています。
つまり、合格のカギは「確実に得点すべき問題を落とさないこと」に尽きます。
論文試験は知識と論理のアドベンチャー
続く論文試験は、産業財産権法に関する知識をベースに、論理的思考力と応用力を試されるステージです。
合格率は27.5%。一見高く見えますが、実際には「問題文の読み取り力」や「条文理解の深さ」が問われる難関です。単なる暗記では太刀打ちできず、「なぜそうなるのか」を説明できるかが勝負を分けます。
口述試験は「ラスボス戦」
最終関門となる口述試験は、試験委員と対面で行われる緊張感MAXの実技試験。合格率は91.7%と高めですが、条文の理解を即座に言葉にできる瞬発力と、メンタルの強さが試されます。ここまでたどり着いた受験生も、油断すれば落ちる可能性がある「真のラスボス戦」です。
令和8年度の弁理士試験は、明らかに合格者を絞る時代の真っただ中にあります。戦略的な学習と覚悟が求められる年になるでしょう。
ここが要注意!「引っかけ問題」&「マイナー条文」
「できる」と「しなければならない」の違いに要注意
弁理士試験の短答では、条文の文言一つで正誤が決まる「引っかけ問題」が多数出題されます。特に、「○○することができる」と「○○しなければならない」の違いは、正解を左右する大きなポイント。
条文をなんとなく覚えているだけでは対応できず、正確な文言の暗記と意味の理解が不可欠です。思い込みや曖昧な知識が命取りになるため、細部へのこだわりが問われます。
マイナー条文でも容赦なし!対策のカギは青本+逐条解説
また、出題頻度の低いマイナー条文も近年は積極的に出題されており、受験生の油断を突いてきます。こうした条文の対策には、TACの基本テキストと、特許庁が出している「青本(工業所有権法逐条解説)」の併読が効果的です。
暗記ではなく、「なぜそう書かれているか」まで踏み込んで理解することで、応用問題にも対応できるようになります。
特許法11番・正答率13%の問題を分析せよ
令和7年度試験では、特許法11番の問題が正答率13%と極めて低く、多くの受験生が引っかかりました。原因は「条文通りに考えれば簡単」なはずの問題に対し、多くの受験生が「引っかけ」に気づかず誤答したことにあります。
このような正答率の低い問題こそ、引っかけやマイナー知識の温床。見直す価値のある良問です。正答率50%以上の基本問題を確実に押さえ、こうしたトラップ問題を丁寧に処理できるかが、合格への分かれ道になります。
【参考動画】LEC弁理士講座、宮口聡先生の解説「【上級者向けシリーズ】短答R7-特実11(ニ)の解説」
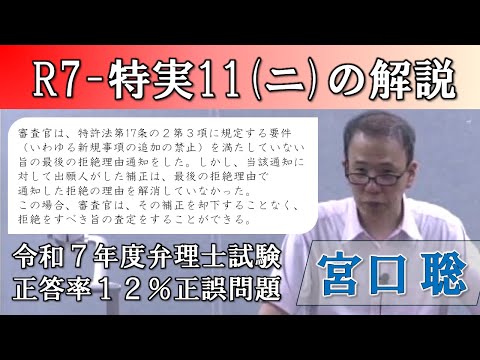
2025/06/04 #知的財産 #特許 #宮口聡
R7-特実11は、令和7年度弁理士試験の短答本試験において最も正答率の低かった問題です(正答率12%)。正答率が低い原因は枝(ニ)にあります。特許庁の見解は×ですが、〇という考え方もできます。つまり、正誤がはっきりしないのです。このような枝であっても、「1つ選べ問題」であれば、他の4枝との絡みで答えを割り出すことができますが、R7-特実11は「いくつあるか問題」なので、答えを割り出すことができず、受験生にとっては極めて酷と言わざるを得ません。本枝を〇とする根拠、及び×とする根拠の両方について解説するとともに、どういう問題文にすれば疑義が生じなかったのかについても言及しています。【R7-特実11(ニ)】
審査官は、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。板書:https://www.ryuka.com/jp/wp-content/u…
引用 YouTube
TACのデータリサーチで見えた落とせない問題
正答率47%以上の問題は合格者の共通知識
TACのデータリサーチでは、毎年受験生の解答傾向と正答率が公開されています。その中でも正答率47パーセント以上の問題は、いわゆる合格者が確実に正解している問題群。
ここを落とすと、合格可能性は一気に下がります。実際、多くの合格者はこれらの問題を8割以上の精度で取り切っており、まさに得点源として絶対に外せないラインです。
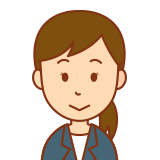
弁理士試験の最新情報は、大手スクールの実力派講師による「弁理士講師ブログ」がおすすめです↓
合格のカギは基本問題を確実に取る力
弁理士試験では、難問を解けることよりも、基本的な問題を確実に正解する力が問われます。
特に短答試験は39点前後がボーダーで、合格を左右するのは取りやすい問題をどれだけ落とさずに得点できるか。高正答率の問題こそ、本番で確実に得点しておくべき必須項目といえます。
正答率47%未満の問題は引っかけや審査基準系
一方で、正答率47パーセント未満の問題は、多くが引っかけ要素を含むか、マイナー条文や審査基準を前提とする難問です。
こうした問題に時間を費やしすぎると、効率が悪くなりがち。大切なのは、こうした問題を見極める力を養い、過度に深入りせず、まずは取りやすい問題を取りきる姿勢。限られた勉強時間の中で、データに基づいた戦略的な学習を行うことが、合格への近道となります。
\速読は資格取得、仕事にも役立つ/
![]()
累計受講者25万人を突破!資格試験に役立つ講座【速読解Biz】はこちら→
令和8年度、どう勉強すれば合格できるのか
地上戦で条文を深く読み解く
令和8年度の弁理士試験に向け、TACの小松純先生が提唱するのは、二段構えの戦略的学習法です。
まず重要なのが、条文を一つひとつ丁寧に読み解く「地上戦」。産業財産権法に関する全条文の要件・効果を正確に理解し、語句の違いにも敏感になることが求められます。引っかけ問題やマイナー論点に対応できる土台は、ここで築かれます。
パラシュート攻撃で得点力を強化
次に実践すべきは、過去問や通達を狙い撃つ「パラシュート攻撃」。枝別過去問を使い、頻出論点や正答率の高い問題を繰り返し解くことで、本番に強い得点力と瞬発力を身につけます。
理解した条文の周辺知識を確認しながら、知識の穴を埋めていくスタイルです。難問対策よりも、確実に取るべき問題を落とさない姿勢が重要です。
勝負は7月、今から成長曲線を描け
特に重要なのは、7月からの本格的な学習再スタート。前年度で35点前後だった受験生にとっては、ここからが巻き返しのチャンスです。
基本講義でインプットを固め、枝別過去問を経て、年明け以降は青本準拠の過去問や模試で実戦力を高めていくのが王道の学習ステップ。今こそ、計画的に成長曲線を描くタイミングです。

まとめ
弁理士試験は、挑戦と挫折、そして再起の連続です。TACの小松純先生が伝える「人生七転び八起き」という言葉は、まさにこの試験に挑むすべての受験生へのエールです。
試験制度の厳しさを正しく理解し、条文の読み込みと過去問演習を戦略的に組み合わせることで、確実に合格への道は開けます。今の実力がどうであっても、ここからの積み重ね次第で合格は十分可能です。焦らず、しかし手を止めず、一歩一歩前に進んでいきましょう。