2025年12月に行われた公認会計士・短答式試験の解答速報です。
なお、12月の短答式試験から、配点・実施時間等が変更になります。受験される方は十分に注意してください。
大手予備校の解答速報
LEC公認会計士講座(ボーダー予想あり)
公認会計士試験の指導歴32年のLEC。LEC公認会計士講座では解答速報のほか、徹底分析した解説講義の無料動画配信、模範解答集プレゼントなどを実施します。
速報版!試験講評とボーダー予想
【森村礼二郎先生の講評&ボーダー予想】企業法

【二ノ宮真典先生の講評&ボーダー予想】管理会計論
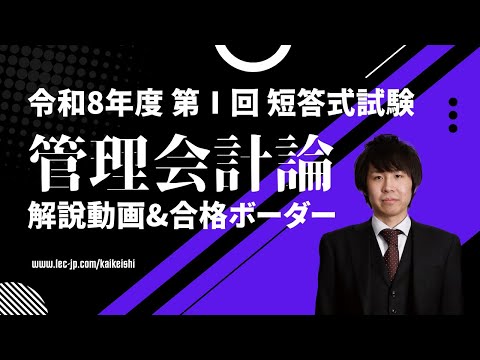
【日下大輔先生の講評&ボーダー予想】監査論

【影山一人先生の講評&ボーダー予想】財務会計論

速報版!全体の講評&合格ボーダー
【橘里奈先生の講評動画】全体の講評&合格ボーダー、短答式試験当日の夜に収録されたもの。
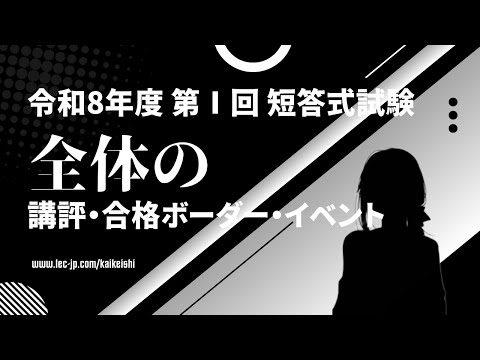
2025/12/15 #公認 #会計士 #公認会計士
2025年12月実施 公認会計士 短答式試験 「全体の講評&合格ボーダー」と「イベント&講座情報」です。
詳細⇒ https://www.lec-jp.com/kaikeishi/juke…
引用 YouTube
LEC本試験分析会動画
【LEC会計士】令和8年 第Ⅰ回 短答式試験 分析会(2025.5.31実施)(前回のものです。今回分は公開待ちです)

2025/06/02 #公認 #会計士 #公認会計士
2025年12月実施の短答式試験について、講師による詳細な分析と、今後に向けた受験対策をガイダンスします。2025年12月の短答式試験受験をご予定の方も、ぜひご視聴ください。
引用 YouTube
資格の大原・公認会計士講座(ボーダー予想あり)
資格の大原では解答速報の公開のほか、「問題・解答解説 閲覧サービス」の実施も。
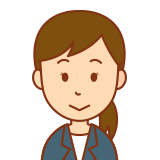
受講料が大幅に割引になる「選抜特待生試験」も実施します
クレアール公認会計士講座
「公認会計士試験、非常識合格法」でおなじみのクレアール。人気書籍のプレゼントも。
CPA会計学院(ボーダー予想あり)
\あの講座が期間限定の大幅割引/
→LECタイムセールはこちら![]()
CPA会計学院では、解答速報の公開に加え、ボーダー予想の公開も。解答速報ページはこちら
速報版!講評と解答解説
【企業法】

【管理会計論】

【監査論】

【財務会計論】
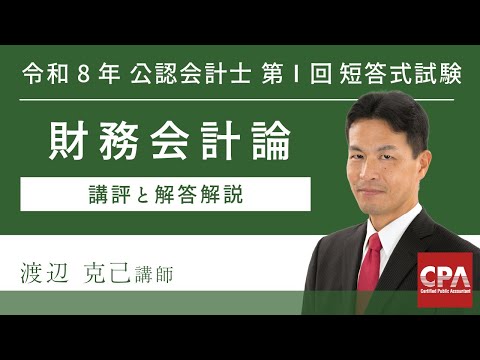
速報版!短答ボーダー予想
【植田講師の短答ボーダー予想】本試験2日後に公開されたものです。
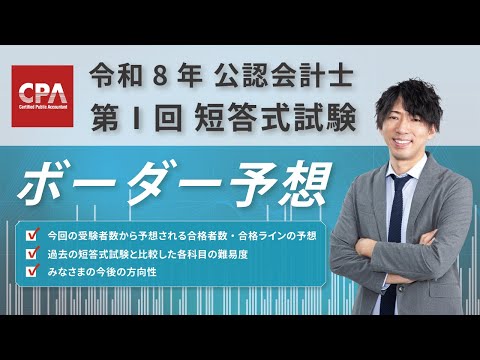
2025/12/16
CPAでは短答ボーダー予想を公開しています。
・過去の短答式試験と比較した各科目の難易度
・今回の受験者数から予想される合格者数・合格ラインの予想
・会計士受験生必見!今後の学習の方向性について
引用 YouTube
資格の学校TAC・公認会計士講座(ボーダー予想あり)
TAC公認会計士講座では、解答速報の公開のほか、ボーダーライン予想の動画も。TAC解答速報はこちら
速報版!講評とボーダー予想
【企業法】令和8年第Ⅰ回短答式試験 講評・予想ボーダー

【管理会計論】令和8年第Ⅰ回短答式試験 講評・予想ボーダー
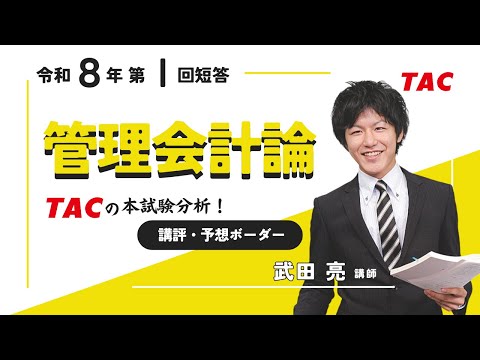
【監査論】令和8年第Ⅰ回短答式試験 講評・予想ボーダー

【財務会計論-理論】令和8年第Ⅰ回短答式試験 講評・予想ボーダー
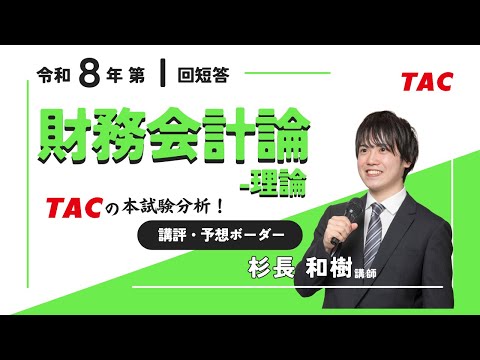
【財務会計論-計算】令和8年第Ⅰ回短答式試験 講評・予想ボーダー
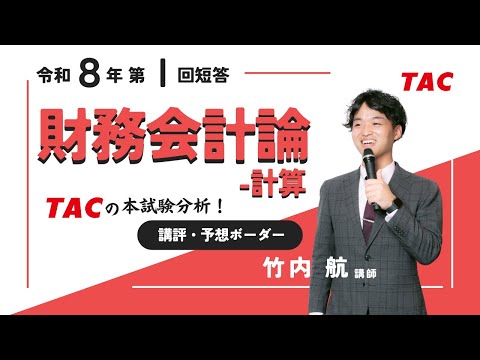
【ボーダー予想】令和8年第Ⅰ回短答式試験 ボーダー予想動画
【久野講師の短答ボーダー予想】本試験2日後に公開されたものです。
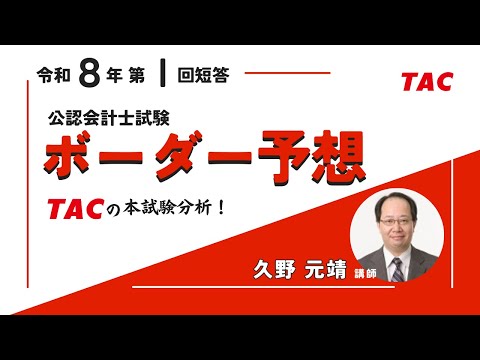
2025/12/16 #公認会計士 #TAC #短答
令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験における、TACのボーダー予想動画です。
引用 YouTube
短答突破後、次は論文!12月合格見込みのあなたが8月本試験に向けて今すべきこと
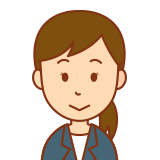
12月の短答式試験、お疲れ様でした!でも本番はここから
短答式試験は通過点、論文式試験が本当の勝負
12月の短答式試験を受験された皆さん、本当にお疲れ様でした。ここまでの努力と頑張りに、まずは拍手を送りたいと思います。
しかし、皆さんご存じの通り、公認会計士試験は「短答合格=ゴール」ではありません。むしろ、ここからが本当の勝負――8月に控える論文式試験に向けた戦いが始まります。
合格発表(6月中旬)を待ってからでは遅い
「まずは結果を待ってから」と考えてしまう方もいるかもしれません。でも、ここに落とし穴があります。論文式試験に必要な実力は、短答とはまったく別物。合格発表の時期から準備を始めても、正直なところ“間に合わない”のです。
なぜなら、論文は知識の量や正誤の判断力だけでなく、論理的な文章構成力・思考力・応用力が問われます。つまり「答案の書き方」を含めた訓練が必須。これらの力は、一朝一夕では身につきません。
今この6~8月が、合否を決める「勝負の3か月」
この6月から8月の約3か月間が、公認会計士試験の“最重要期間”です。短答の知識が残っている今だからこそ、スムーズに論文対策へ移行できる。ここで一歩踏み出せるかどうかが、論文本番での合否を大きく左右します。
LEC公認会計士講座の論文対策講座や答練も、本試験仕様で構成されており、実戦力を鍛えるには絶好のタイミング。自信を持って「勝負の夏」に挑むためにも、今この瞬間からスタートを切りましょう。
【参考動画】LEC公認会計士講座、2025年 短答からの論文本試験に向けた学習切り替え法(2025.5.26実施)
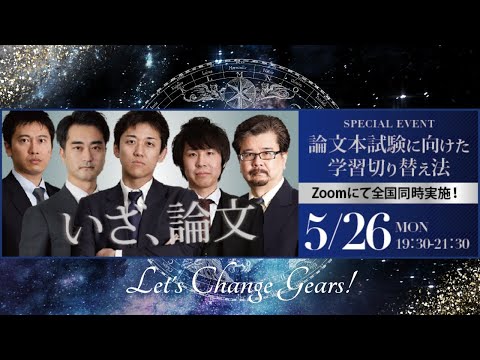
2025/05/27 #公認 #会計士 #公認会計士
25年12月短答を受験後に挑戦する3ヵ月後の論文に向けての学習切り替え法です。
レジュメ→ https://www.lec-jp.com/kaikeishi/pdf/…
【掲載期間:2025/12/31まで】
引用 YouTube
論文式試験は「別物」だと心得よ
短答と論文はまったくの「別物」
短答式試験では、知識の網羅性とスピード勝負が求められました。言い換えれば、「知っているかどうか」が問われる試験です。しかし、論文式試験は違います。知識だけでは太刀打ちできません。
論文式試験で試されるのは、思考力・判断力・応用力・論述力。とりわけ企業法・監査論などの理論科目では、限られた時間の中で「いかに筋道立てて説明できるか」が勝負を分けます。条文の趣旨や背景、制度の目的まで踏み込んだ表現が求められ、「なんとなく知っている」だけでは得点に結びつきません。
監査論・企業法など理論科目で差がつく
企業法では、制度の理解や趣旨の説明を求められる「制度説明型問題」や、学説・判例をもとに自説を述べる「論点型問題」が出題されます。どちらの形式であっても、単なる暗記では通用せず、論理的に説明する力が問われます。
監査論では、実務的な場面を想定した事例問題や、監査の考え方そのものを問う理論問題が出題されます。ここでも、「理解していることを、相手に伝わる形で書く力」が不可欠です。
計算科目も「答案作成」の練習が必須
計算科目(財務会計論・管理会計論・租税法など)についても、短答時の力をそのまま持ち込んでは不十分です。特に論文では、「計算過程をどう表現するか」が問われます。計算の正確性だけでなく、「見やすく」「伝わる」答案が求められるのです。
また、管理会計や財務管理では、資料の読み取り力や問題の意図をくみ取る力も重要になります。短答と比べて情報量が多いため、題意を素早く把握する力や、時間配分のセンスも問われます。
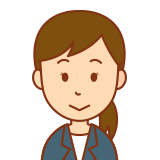
「論文式は別物」だと心得よ。
論文式試験に必要な3つの力とは?
短答式試験を突破した皆さん、次に立ちはだかるのが8月の論文式試験です。ここで問われるのは単なる知識量ではありません。合格するためには、以下の「3つの力」が必要不可欠です。
【①問題文読解力】=問われている論点を見抜く力
論文式試験は、「知っているかどうか」だけでなく、「何をどう書くべきか」を判断する力が問われます。問題文を読んだ瞬間に、出題者が何を聞きたいのか、どこがキーポイントかを素早く見抜く力=「読解力」が必要です。
たとえば監査論の第一問では、学説や制度趣旨を論じる論点型の問題が多く出題されます。問われているテーマの核をつかみ、枝葉に惑わされずに本質的な論点を抽出できるかが、得点を大きく左右します。
【②答案構成力】=論点の優先順位や流れを整理する力
読解した内容をただ並べるだけでは不十分です。次に必要なのが「構成力」。論点をどの順序で、どのような流れで記述するかという構成を練る力です。
企業法などの制度説明型の問題では、条文→趣旨→あてはめという論述の枠組みが鉄則。これを守らないと、知識があっても点数につながりません。監査論の事例問題では、状況の分析から導かれる判断を、筋道立てて論述することが求められます。
【③答案作成力】=時間内に論理的に書き切る力
試験本番では、制限時間内に1,000字近い文章を論理的に書き切る「アウトプット力」が勝負になります。特に重要なのは、「制限時間内に答案を完成させる力」です。
財務会計論や租税法などの計算問題でも、答案作成力が問われます。途中まで解けていても、答案に反映されなければ点はもらえません。本試験仕様の答練で時間を計って解くなど、実戦的な訓練を通して、「書ききる力」を養うことが必要です。

いきなり書かない!論文式対策の正しいステップ
論文式試験の勉強は、「とりあえず書いてみよう」ではうまくいきません。まずは「考える力」を鍛え、徐々にアウトプットにつなげていくことが重要です。ここでは、LECが推奨する論文対策の3ステップをご紹介します。
ステップ1 問題文の読み方・論点抽出練習(過去問分析)
論文式試験で最初に求められるのが、「問題文を正しく読む力」です。
どの論点が問われているのか?どのキーワードに注目すべきか?
こうした視点を身につけるためには、まず過去問を分析してみましょう。
特に企業法・監査論といった理論科目では、条文の趣旨や学説の立場を踏まえた読み取りが求められます。問題文を読んで「どこが採点ポイントか?」を意識しながら、論点を抽出するトレーニングから始めましょう。
ステップ2 答案構成トレーニング(論点カード、構成メモ活用)
問題文の読み取りができるようになったら、次は「どう書くか?」を考える答案構成トレーニングです。
そこで「論点カード」や「構成メモ」を使った練習をおすすめします。
これは、自分の頭の中で論点の優先順位を整理し、答案の流れを論理的に組み立てるための訓練です。
例えば監査論であれば、問われた事例に対して「どの監査基準を適用すべきか?」を判断し、順序立てて記述する力が問われます。いきなり答案を書き始めるのではなく、「設計図」を描いてから書くことが、質の高い答案につながります。
ステップ3 実際に答案を書く演習(時間配分を意識)
最後に、実際の答案作成に進みます。この段階では「時間配分」がカギです。
本試験では、限られた時間の中で、複数の論点に的確に答える必要があります。
そのためには、「どこに時間をかけるか」「どこは簡潔にまとめるか」のメリハリが重要です。
LECの「論文グレードアップ答練」や「プレ答練」は、本試験の形式や時間感覚に慣れるのに最適。答練を繰り返す中で、スピードと正確性のバランスを養っていきましょう。
「何も書けない」を防ぐために、今やるべきこと
論文式試験では、「分かっているはずなのに、いざ書こうとしたら何も出てこない…」という受験生が毎年続出します。これは知識の不足というより、「書く準備ができていない」ことが原因です。今この6月から、8月の本試験に向けて“書ける”力を養成するためには、次の3つの対策が必須です。
理論科目のストックを増やす、監査論・企業法が勝負
監査論・企業法は、論文式で最も差がつきやすい理論科目です。対策としては、まず頻出テーマに絞って、論点のストックを「書ける形」で積み上げていくことが重要です。キーワードを押さえつつ、自分の言葉で要点をまとめる練習をしましょう。
特に監査論では、事例問題でも「実は見たことがある論点」がほとんどです。過去問や答練を使って“引き出し”を増やすことが、合格答案への近道です。
会計学の理論問題は【型」で攻略せよ
会計学でも、第4問・第5問などで理論問題が出題されます。こちらも闇雲に暗記するのではなく、「テンプレート化」して対応するのが有効です。
例えば、「定義→趣旨→結論」という流れを意識すれば、ある程度パターン化した書き方ができます。LECのグレードアップ答練で繰り返し練習すれば、自然と型が身につくはずです。

計算問題も「見直し方」を変えるべし
論文式の計算問題は、短答とは異なり、ミスのリカバリー力や答案構成力が問われます。重要なのは、「できた・できなかった」だけでなく、「なぜ間違えたか」「どの資料を見落としたか」を分析すること。
LECのプレ答練や過去問を使って、「2時間でどう答案を構成するか」「見直しをどうするか」といったプロセスを意識した演習が必要です。
【ポイント】ストック・型・プロセスを意識せよ
「論文式は思考力と表現力の試験」とよく言われますが、最初から“自由に書ける人”はいません。今の時期に、ストックを増やし、型を覚え、プロセスを繰り返す。この地道な積み重ねが、「本番で手が止まらない」力を育ててくれます。
焦らず、一つ一つの論点を“書ける”形にしていきましょう。
論文式試験は「型」と「再現性」が命
論文式試験で合格するために最も重要なのは、「型」を徹底的に叩き込むこと、そしてその「型」をどんな問題にも“再現”できる力です。問われ方が変わったとしても、毎回同じように論理的な答案を組み立てられる「汎用性」が、試験本番での安心感と得点力につながります。
問題提起→規範定立→あてはめ→結論の「流れ」を徹底せよ
監査論や企業法といった理論科目では、思考力・判断力・論述力が試されます。ここで差をつけるためには、以下の“論文答案の型”をしっかり身につけておく必要があります。
この構成が自然と手が動くレベルで身についていれば、初見の問題でも焦ることなく対応できます。
計算問題でも「再現性」がカギ
計算科目であっても、ただの「作業」では終わりません。出題形式が少し変わっただけで手が止まってしまう人は、真の理解に至っていない可能性があります。過去問や答練を通じて、何度も「自分で解ける」ことを確認し、再現性の高い解法を身につけることが大切です。
さらに、途中までしか解けなくても「途中点」を拾える答案を意識しましょう。完答できなくても、得点を積み重ねる姿勢が合格に直結します。
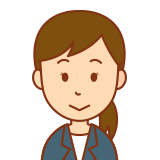
「型」を体に染み込ませ、それを本試験で「再現」する力を磨くことが、論文式試験合格の最大のカギです。

6月~8月の過ごし方がすべてを決める
12月の短答式試験を終えた今、最大の山場である「論文式試験」が目前に迫っています。6月中旬の短答合格発表を待ってから対策を始めるのでは、明らかに遅すぎます。この6月から8月こそが、公認会計士試験の合否を決定づける“勝負の3か月”です。
1日1答案、特に理論科目で「書く体力」をつける
論文式試験では、知識を頭に入れているだけでは不十分です。「制限時間内に、自分の言葉でアウトプットできる力」が問われます。特に監査論・企業法・租税法といった理論科目は、書く力・表現力がそのまま得点に直結します。
そのため、6月からは「1日1答案」を意識した学習が重要です。最初はうまく書けなくても、答案構成→実際に書く→添削・見直し、のプロセスを繰り返すことで、徐々に「書く体力」と「構成力」が身についていきます。
暗記から“使える知識”へ転換する
短答式では、正誤判断に必要な断片的知識で突破できたかもしれません。しかし論文式では、それらの知識を自分で再構成し、筋道を立てて説明する力が求められます。つまり、暗記型から“使える知識”への転換が不可欠です。
特に、理論科目は「型に沿った思考法」や「論点ごとのテンプレート」を使って、再現性の高い答案を目指しましょう。会計学・管理会計など計算科目であっても、ただ解くだけでなく、答案に落とし込む意識が重要です。
本試験日から逆算したスケジュールを今すぐ立てる
論文式試験は8月中旬に行われます。つまり、今が「本番から逆算して学習計画を立てる」最後のチャンスです。
まずは主要6科目の中で、自分の得意・不得意を洗い出し、重点配分を決めましょう。次に、週単位での目標(例:今週は監査論の頻出論点を3つ仕上げる)を立て、実行と振り返りをセットで行います。
LECの論文グレードアップ答練やプレ答練、公開模試といった教材を活用すれば、実戦形式で自分の弱点や改善点が見えてきます。論文対策に正解はありませんが、「実際に書いて改善する」を3か月繰り返せば、着実に本試験に間に合う実力がつきます。
【まとめ】論文式試験の勝敗は「今」決まる
短答式試験を終えたあなたにとって、次に待ち受ける論文式試験は、まったく異なるステージです。単なる知識の有無ではなく、「問題文を読み解き」「答案を構成し」「時間内に論理的に書き切る」という高度なアウトプット力が求められます。
特に6月から8月の3か月間は、短答の疲れを引きずることなく、論文に“ギアチェンジ”することができるかどうかで、合否が大きく分かれます。この時期をどう過ごすかが、まさに合格を左右する決定的要因です。
書けなければ点にならない、でも「書けるようになる」には時間がかかる——だからこそ今すぐにでも、論文式対策をスタートさせましょう。
LEC公認会計士講座では、この論文式試験を突破するために必要な力を、段階的に育成する答練・講義・教材が揃っています。短答と論文を熟知したプロ講師陣が、今この時期に必要なノウハウを惜しみなくレクチャーします。
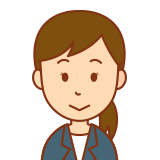
合格をつかむのは、「今、この瞬間に一歩を踏み出せた人」です。

論文試験の突破なら、LEC公認会計士(論文対策講座)
短答合格者に「今、必要なすべて」が揃っている
LECの論文対策講座は、単なる「知識のインプット」ではなく、「本番で書ける答案力」を養成することに特化しています。
特長1 合格に直結する答案力を段階的に養成
LECでは、「問題文の読解→答案構成→答案作成」という論文式試験のプロセスを3ステップで徹底トレーニング。過去問分析・論点整理・答案構成メモなど、すべてが“書ける力”に直結します。
特長2 プロ講師による徹底指導
短答・論文の両方を知り尽くした実力派講師陣が、答案の添削・フィードバックを通じて、あなたの課題を的確に指摘・改善。疑問もすぐに解消でき、独学では得られない「安心感」と「納得感」が得られます。
特長3 圧倒的な演習量で“書く体力”を養う
論文式は「練習量」が命。LECの答練・模試では、理論・計算ともに実戦形式で繰り返し演習。本試験を想定したタイムトレーニングで、合格レベルのスピードと再現力が自然と身につきます。
特長4 合格までの学習戦略も完全ナビゲート
「短答の結果を待っていては遅い」今この時期から、論文合格に向けた学習スケジュールや重点テーマを明確に示し、最短ルートで合格へ導きます。
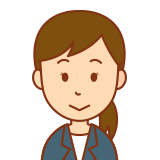
今こそ、論文対策のスタートを
短答の知識を「論文で得点できる力」に変えるためには、今すぐのスタートが不可欠です。LECで、“確かな合格力”を一緒に築きませんか?
みんなの解答速報掲示板
受験された方の感想(難易度、合格ライン予想など)をお待ちしています。
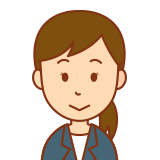
解答状況・試験の難易度・ボーダー予想など、お聞かせください

